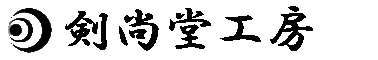
剣道具のQ&A
《剣道具に関してのお悩みがございましたら、メール・FAXでお知らせください》
面関連
- Q.面の内側が狭いので顔がいれにくい。
- A.面を面の中にたたき押し込むように入れる 半日放置


- Q.面の内輪が大きすぎる
- A.毛布等を利用し内輪、内側にいれます 厚さ5㎜程度から調整してください


- Q.内輪がたれている為あごの安定がわるい
- A.内輪の縫い方を説明します




- Q.汗が多い為、面が壊れやすい
- A1.ビニール系の素材を利用し内輪、内側にいれます 汗を内輪内にとどめます

- A2.面淵の赤ところを数回厚く塗ります



- A3.アゴの強化




- Q.コンタクトレンズが難しい時期にメガネを使えるようにしたい
- A.内輪を切ります



- Q.面布団を短くしたい
- A.面布団を切ります ※修理教室参照


甲手関連
- Q.甲手が臭い
- A.甲手を洗います 洗えば臭いがなくなります




防具用香スプレー クリー二ング後が有効
- Q.稽古後、手・体など汗臭い
- A.手・体など専用消臭・抗菌プレー

- Q.手の内の大きさが合わない
- A.手の大きさに合わせた手の内に交換する ※修理教室参照



- Q.面を打たれると痛い
- A.面の内側にサポーターを入れます
低反発素材+生ゴム+生革 ※ほとんど痛くありません




- Q.甲手を打たれると痛い
- A.甲手の内側にサポーターを入れます
低反発素材+生ゴム+生革 ※ほとんど痛くありません




- Q.防具に型をつけたい、布団がふかふかして痛い
- A.型をつけたい部分、ふかふかしている部分にスプレーします 水性硬化液


胴関連
- Q.胴幅が狭い・胴幅が広い
- A.樹脂系(ヤマト胴)の場合
胴の内側に竹を入れべルトなどで回りを固定し半日ほど放置します

- A.竹胴系の場合
1.新聞・タオルなどを水で濡らし胴の裏側に貼り付ける様にします
2.胴の内側に竹を入れべルトなどで回りを固定します
3.ビニール袋に胴を入れ1日~2日様子をみながら放置します
4.ビニール袋から胴を出し1日~2日天日干し
5.幅が固定されたら竹を取り出します
注) 水に濡らしすぎると漆がはがれる恐れがありますので十分注意して下さい


- Q.(竹胴・漆系)胴のすりきずなど胴台をきれいにしたい
- A.ワックスなどを胴台全体に塗布し研磨用フェルトを取り付けたハンドモーターで磨きます
深いキズは無理です 研磨しすぎに注意







- Q.胸の革の剥げをきれいにしたい
- A.飾り糸系は早染めインク、牛革系は早染めインクまたはカシュー カシューの場合は薄く伸ばしながら塗る











防具の選び方・手入れ方法
- Q.防具の選び方は
- A.身長に合った防具を選んでください ※サイズ表参照
・顔の寸法は必ず計る
・ややキツメがよい
・顔の寸法が合っていれば自然と物見が合います
注)140cm前後の身長に普通サイズ(L)は無理 (L)は170cm前後の身長に合った防具です
注)物見が合わないと頭を上下に動すことになり目的物がよく見えないことになります
※物見・ややキツメがもっとも重要

- Q.防具の手入れ方は
- A.防具購入後、必ず壊すくらいの勢いで腰を入れ面・甲手・垂をもみあげること
- Q.防具が硬くて使い難い
- A1.汗(塩)・硬化液等を抜くために水洗いをする
A2.乾いた後トンカチでたたきあげ腰を入れもみあげる
布団にこしができ使いやすい防具に変わります
注)硬い防具が好きな方は何もしないほうが良いと思います
注)防具の手入をしないと1~2年間は痛い思いをすることになります








- Q.防具が色あせた ※修理教室参照
- A.防具専用藍色復元液

- Q.道着・袴が色あせた ※修理教室参照
- A.道着・袴専用藍色復液

- Q.水洗いしても道着・袴の藍色をとどめたい ※修理教室参照
- A.道着・袴専用藍色止液

防具の修理関連
- Q.防具を自身で直したい ※修理教室参照
- A.針で縫うより防具が汗で濡れても剥がれない両面テープを利用すると良い
素材の材料は古着・合成革などを利用します


※絶対に接着ポンドは不可です、修理すらできなくなります
- Q.綿生地の手の内
- A.既存の手の内で型をとり綿の生地を2枚重ねすれば鹿皮とほぼ同じ位の強度があります
素手感覚で試合用に最適です
へり皮をつけなければ簡単です








- A.ヘリ革の付け方







- Q.アイロン圧着テープの使用法
- A.綿の生地にアイロン接着テープをつけアイロン接着します








- Q.修理道具の作成
- A.指ぬきを作ってみよう











- Q.型の作成
- A.型を作ってみよう (鉄型不要・プレス機も不要)
型をビニールなどで写し紙型を作ります
紙型を紙に写し素材の材料にノリを張る












面紐関連
- Q.面紐がうまく結べない
- A.面紐ストッパーを作ろう
面紐ストッパを布団につける際はアイロン接着、両面テープ、まわりを縫う、などの方法があります





- Q.面紐・胴紐が汗などで固くなり結びにくい
- A.洗う事で解消されます




- Q.面紐を短くしたい
- A.紐を切って結びます






竹刀関連
- Q.竹刀が壊れたら
- A.《ささくれ》 壊れたらそのつど修理します
紙やすりなどでささくれ部分を削ります



※強くんは接着液のようなもので通常の2倍以上竹刀が長持ちします
- A.《竹組み換え》 竹刀の竹が1本折れたら買い替えるのではなく組み換えを行います
全ての部品を取り外し折れた竹をさし換えます
部品を取り外す際は上から下に抜くように外します
取替える側の竹にチギリの印をつけノコギリできりこみをいれます
チギリを取り外し、取替える側の竹と折れていない竹とを組み合わせます
竹がバラケないようにビニールテープなどで柄の部分を巻きつけます
柄革を入れる際は竹がバラケないように鍔(つば)などで固定します
部品を入れる際は中〆革・先ゴム・先革の順番で入れて下さい










- Q.柄革を短くしたい
- A.柄革を切って折り返します






- A.柄革を切って縫います








- A.柄革を切って折り返し編み込みます
















是非ご紹介したい本 《剣道用具マニュアル》
- 剣道用具マニュアル




道着・袴の着用のしか方・たたみ方 手拭のつけ方
竹刀の修理の方法などなどイラストにより丁寧に説明してくれている本です